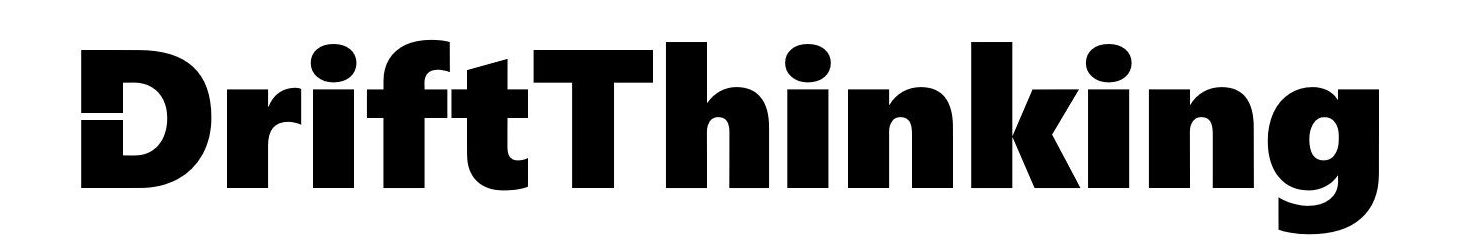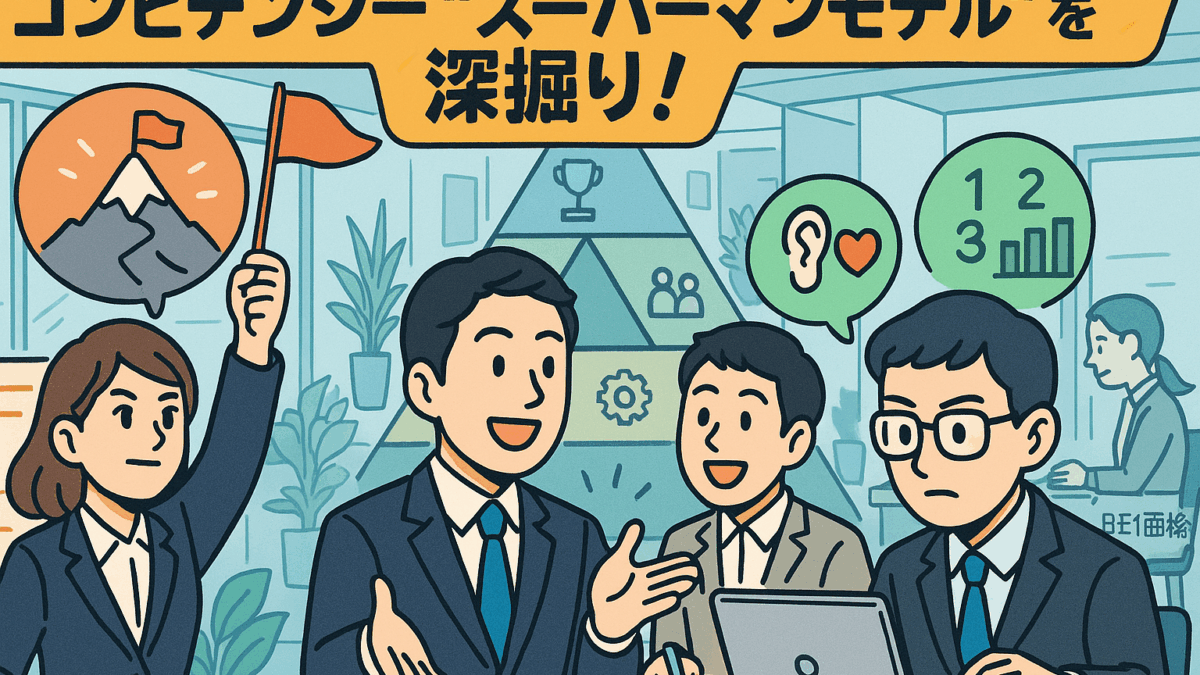前回のブログでは、現代の人材マネジメントにおいて不可欠な概念である「コンピテンシー」について、その重要性を概観しました。今回は、さらに一歩踏み込み、ライル・M・スペンサーとシグネ・M・スペンサーの金字塔的著作『コンピテンシー・マネジメントの展開』を軸に、「コンピテンシーとは何か?」を徹底的に深掘りしていきます。なぜ「スーパーマンモデル」と呼ばれるのか?その項目分類やレベル設定はどうなっているのか?そして、コンピテンシーを明らかにする強力なツールである「行動結果面接(BEI面接)」とは何か?これらの実践的な観点から、あなたの仕事やキャリア、そして組織の人材戦略に役立つヒントを見つけていきましょう。
コンピテンシーとは何か?「スーパーマンモデル」の背景
まず、スペンサー夫妻が提唱するコンピテンシーの定義を再確認しましょう。
「ある職務または状況に対し、基準に照らして効果的あるいは卓越した業績を生む原因として関わっている個人の根源的特性」
これは単なるスキルや知識の羅列ではありません。例えば、ある職務で「優れた営業成績」を出している人がいるとします。その成績は、単に「商品知識がある」からだけではなく、「顧客の潜在ニーズを引き出す傾聴力」「困難な状況でも粘り強く交渉する精神力」「常に目標達成を意識し、自ら行動を起こす主体性」といった、その人固有の「根源的特性」に支えられているはずです。この「根源的特性」こそがコンピテンシーなのです。
なぜ、このコンピテンシーが「スーパーマンモデル」と呼ばれるようになったのでしょうか。それは、スペンサー夫妻の研究が、「平均的な業績を出す人」と「卓越した業績を出す人(スーパーマン)」との間にどのような行動特性の違いがあるのかを徹底的に分析することから始まったためです。彼らは、さまざまな職務において、その分野で圧倒的な成果を出している「スーパーマン」たちの行動を詳細に観察・分析し、彼らに共通して見られる思考や行動のパターンを特定しました。その結果、「卓越した業績を生み出す人は、特定のコンピテンシーを高いレベルで持っている」ということが明らかになったのです。
つまり、コンピテンシー・マネジメントとは、単に職務に必要な要件をリストアップするのではなく、実際に「卓越した成果」を生み出している人々の特性をモデル化し、それを組織全体の人材育成や採用、評価に応用していくという、非常に実践的なアプローチなのです。このアプローチによって、組織は単なる「平均」を目指すのではなく、「卓越」へと導かれる可能性を秘めていると言えるでしょう。
コンピテンシーの項目分類とレベル:20項目の「コンピテンシー・ディクショナリー」
スペンサー夫妻は、彼らの研究に基づいて、普遍的に適用可能な20項目の「コンピテンシー・ディクショナリー」を開発しました。これは、コンピテンシーを体系的に理解し、さまざまな職務や状況に適用するための非常に強力なフレームワークです。
これらの20項目は、さらに以下の6つの領域に分類されています。
- 達成・行動領域 (Achievement and Action): 目標達成への意欲や行動に関するコンピテンシー。
- 援助・対人支援領域 (Helping and Human Service): 他者を支援し、協力的な関係を築くためのコンピテンシー。
- インパクト・対人影響力領域 (Impact and Influence): 他者に影響を与え、納得させるためのコンピテンシー。
- 管理領域 (Managerial): 組織やプロジェクトを効率的に管理し、成果を出すためのコンピテンシー。
- 知的領域 (Intellectual): 情報を分析し、問題解決を行うための思考力に関するコンピテンシー。
- 個人の効果性領域 (Personal Effectiveness): 自己管理や自己認識、ストレス耐性など、個人の内的な特性に関するコンピテンシー。
具体的な20項目には、例えば以下のようなものが含まれます。
- 達成思考: 高い目標を設定し、それを達成するために努力する。
- 秩序・品質・正確性への関心: 仕事の質を高め、正確さを追求する。
- イニシアチブ: 自ら率先して行動を起こし、問題解決に取り組む。
- 情報収集: 意思決定のために必要な情報を能動的に集める。
- 対人理解: 他者の感情や動機を理解し、適切に対応する。
- 顧客サービス指向: 顧客のニーズを理解し、期待を超えるサービスを提供する。
- 組織意識: 組織の目標や価値観を理解し、それに貢献する。
- 概念的思考: 複雑な問題を抽象的に捉え、本質を見抜く。
- 分析的思考: 論理的に問題を分解し、原因と結果を分析する。
- 自己統制: ストレスや感情をコントロールし、冷静に対処する。
- 柔軟性: 変化に対応し、状況に応じて行動を変える。
これらのコンピテンシーは、単に「持っているか否か」ではなく、その発揮される「レベル」に応じて評価されます。例えば、「達成思考」というコンピテンシー一つをとっても、「言われたことを期日通りにこなすレベル」から「前例のない高い目標を自ら設定し、周囲を巻き込みながら達成するレベル」まで、その発揮度合いには大きな幅があります。一つ一つの項目には、レベルを分類するための具体的な表現があり、特定の個人の価値観によるレベルイメージとは一線を画していることも極めて重要です。
コンピテンシー・ディクショナリーは、組織が求める人材像を明確にし、採用、評価、育成の各プロセスにおいて共通の尺度で人材を評価するための強力なツールとなります。各職務や役職に求められるコンピテンシーとそのレベルを明確にすることで、従業員は自身の強みと弱みを把握し、具体的な能力開発の方向性を定めることができるのです。
コンピテンシーを明らかにする最強のツール:行動結果面接(BEI面接)
さて、コンピテンシーが個人の「根源的特性」であるとすれば、それをどのように見極めれば良いのでしょうか。単なる「やる気があります!」という自己申告や、一般的な面接での表面的な回答では、その人の真のコンピテンシーを把握することは困難です。そこで登場するのが、スペンサー夫妻が開発し、その有効性が高く評価されている「行動結果面接(Behavioral Event Interview: BEI面接)」です。
BEI面接は、候補者や対象者の過去の具体的な行動や経験に焦点を当てて質問を深掘りすることで、その人がどのような状況で、何を考え、どのように行動し、その結果どうなったのかを詳細に引き出す手法です。これは、単なる知識やスキルの確認ではなく、その人の「根源的特性」、つまりコンピテンシーがどのように発揮されたかを探るためのものです。
BEI面接では、STARメソッド(またはSTAR-Lメソッド)と呼ばれるフレームワークがよく用いられます。
- Situation(状況): その出来事が起こった具体的な状況や背景を尋ねます。
- Task(課題・目標): その状況で、あなたに与えられた課題や、達成しようとした目標は何でしたか?
- Action(行動): その課題や目標に対して、あなたが「具体的に」どのような行動をとりましたか?(ここが最も重要です。抽象的な回答ではなく、具体的な行動を深掘りします。)
- Result(結果): その行動の結果、何が起こりましたか?どのような成果が得られましたか?
- Learning(学び・教訓): その経験から何を学びましたか?次に活かせるとしたら何ですか?(これは必須ではありませんが、より深い洞察を得るために有効です。)
例えば、「困難な目標を達成した経験について教えてください」という質問に対し、BEI面接では次のように深掘りしていきます。
面接官:「どのような状況で、その目標は与えられたのですか?具体的な目標値は何でしたか?」 候補者:「〇〇の状況で、売上目標が前年比150%に設定されました。」
面接官:「その目標達成に向けて、あなたが具体的にとった行動は何ですか?チームメンバーとの役割分担は?工夫した点は?」 候補者:「まず、市場調査をやり直し、新たなターゲット層を特定しました。その後、これまでとは異なる営業戦略として、オンラインセミナーを〇回開催し、個別相談会を〇件実施しました。最初は狙った結果につながらなかったので、悩みました。そこで、セミナー後のアンケートで得られた課題に注目すべきと考え、毎週月曜日にチーム全員で情報共有会を開き、改善策を検討しました。」
面接官:「その結果、どうなりましたか?目標は達成できましたか?」 候補者:「はい、最終的には目標を120%達成できました。特に、新規顧客獲得数が前年比200%に伸びました。」
面接官:「この経験から、どのような学びがありましたか?」 候補者:「困難な目標ほど、チームでの情報共有と柔軟な戦略変更が重要だと学びました。また、従来のやり方にとらわれず、新しいアプローチに挑戦することの大切さを実感しました。」
このように、BEI面接では「なぜそうしたのか?」「他にどのような選択肢があったか?」「そこから何を学んだか?」といった質問を繰り返し、候補者の行動の裏にある思考プロセスや動機、そしてコンピテンシーの発揮度合いを明らかにしていくのです。この手法は、採用面接だけでなく、人事評価や能力開発のフィードバック面談など、さまざまな場面で応用されています。
WithSTART™におけるコンピテンシーの「超深掘り」の可能性
さて、ここで弊社の「WithSTART™」サービスに目を向けてみましょう。WithSTART™は、DriftThinkingが提供する実践伴走型サポートサービスです。これは、「新しい挑戦に本気で取り組みたい」個人や組織を対象としており、起業や新規事業の立ち上げ、キャリアの再設計、学び直し、社内プロジェクトの始動など、さまざまな「新しいスタート」をサポートします。スペンサー夫妻のコンピテンシー理論を深く理解することで、WithSTART™がどのようにコンピテンシーを「超深掘り」し、企業様の採用成功に貢献できるかが見えてきます。
現在のWithSTART™サービスは、OKRへのチャレンジの場を利用して、実際の業務環境での「コンピテンシー」を追いかけていきます。これはまさに、スペンサー夫妻が提唱する「根源的特性」としてのコンピテンシーを、実践の場で評価しようとするWithSTART™の強みと言えるでしょう。
OKRへのチャレンジ状況をリアルタイムで見ていくアプローチは、まさにBEI面接の実践版とも言えます。サービス提供期間中に、企業様はプロジェクト参加者が実際の業務でどのように課題に取り組み、周囲と協調し、新しい知識を習得していくかを直接観察することができます。これにより、普段の業務のなかでは見えない、以下のようなコンピテンシーの深掘りが可能になります。
- 達成・行動領域: 未経験の業務に対する「イニシアチブ」や「達成思考」の有無。
- 援助・対人支援領域: チームメンバーとの「協調性」や「対人理解」。
- インパクト・対人影響力領域: プロジェクト推進における「対人影響力」や「説得力」。
- 管理領域: 自身のタスク管理やプロジェクトへの「組織意識」。
- 個人の効果性領域: 予期せぬ問題への「柔軟性」や「ストレス耐性」。
WithSTART™は、候補者が過去の学習や経験で培ってきたコンピテンシーを、”ムーンショット“に向けて挑戦するOKRへの具体的なチャレンジのなかでどのように発揮するかを「行動結果」として明確に評価する機会を提供します。言い換えると、OKRが”ムーンショット”だからこそ、そこに挑戦が生まれて、コンピテンシーを発揮する機会が生まれるのです。そして、企業・チームの組織文化や求める人材像に深く合致する「スーパーマン」を見出し、さらに成長する機会を作り出すことができるのです。
まとめ:コンピテンシーを理解し、卓越した人材を見つけ出す
今回のブログでは、スペンサー夫妻のコンピテンシー理論に深く焦点を当て、「スーパーマンモデル」の背景、普遍的な20項目のコンピテンシー・ディクショナリー、そしてコンピテンシーを明らかにする強力な手法である行動結果面接(BEI面接)について詳しく見てきました。
コンピテンシー・マネジメントは、単に個人の能力を評価するだけでなく、組織が求める「卓越した業績」を生み出す行動特性を特定し、それを採用、育成、評価の全プロセスに組み込むことで、組織全体のパフォーマンスを向上させるための強力なツールです。
あなたの組織は、これらのコンピテンシーをどのように見極め、次の「スーパーマン」を発掘・育成していますか?