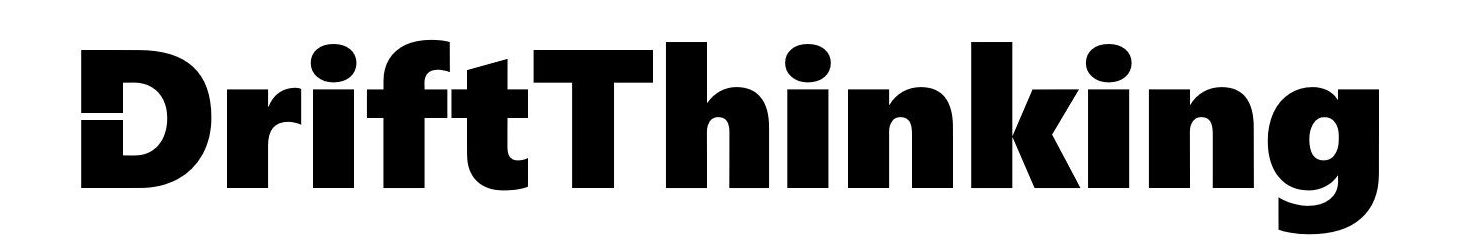近年、多くの企業が導入を進めているOKR(Objectives and Key Results)。これまで、その効果と可能性について、書いてきました。OKRは、組織の方向性を明確にし、短期間で高い成果を追求するための有効なフレームワークです。社員のエンゲージメント向上にも貢献し、現代の組織運営において欠かせない考え方といえます。
しかし、OKRには「限界」もあります。
OKRは「何を達成するか」=Doingの成果に焦点を当てる一方で、「どう達成したか」「どんな行動が成果を支えたのか」といったプロセスの質までは、測りきれないのです。
そこで私たちは、こう問い直します。
成果の背後にある行動の質は、どう可視化できるのか?
その行動を支える「習慣」や「特性」は、どう評価すべきなのか?
その答えの一つが、「コンピテンシー」との統合にあります。
OKRとコンピテンシーの統合が拓く、新しい可能性
OKRが目標の達成度を定量的に測る「成果ドリブン」の仕組みであるのに対し、コンピテンシーは「どのような行動によってその成果が生まれたのか」を評価する基準です。
たとえば、営業部門で「新規顧客20%増」を達成したとしても、「どのような顧客対応」「どのような提案行動」が成功につながったのかまでは、OKRスコアだけでは見えてきません。
コンピテンシーは、こうした行動の「中身」に目を向けます。
たとえば:
- 難題に対する粘り強い交渉力
- 周囲を巻き込むリーダーシップ
- 情報収集への積極性と応用力
これらは、再現性のある成功行動として次の成果を生み出す礎となります。
コンピテンシーでDoingの質を高める
OKRとコンピテンシーを統合することで、次のような価値が生まれます。
- 成果プロセスの可視化: コンピテンシーにより、成果までの道のりを「行動単位」で可視化。成功行動のモデル化が可能になります。
- 実践的な人材育成: OKRが結果を導く目標であるのに対し、コンピテンシーは「その結果に至る行動」を育てる仕組み。明確な行動基準をもとにした育成が可能になります。
- 行動による文化醸成: 組織の価値観を行動レベルで落とし込み、文化として根付かせることができます。
- 評価の納得性向上: OKRが評価から切り離されていても、コンピテンシーによって「行動の良し悪し」を適切にフィードバックでき、社員の納得感が高まります。
DriftThinkingのBeDoing™で実現する統合的アプローチ
私たちDriftThinkingは、OKRとコンピテンシーの統合に基づく独自サービス「BeDoing™」を提供しています。
BeDoing™では、OKRで掲げた目標に対して、四半期ごとの1on1などを通じて、コンピテンシーの発揮状況を丁寧にモニタリング。行動のフィードバックループを回すことで、個々の行動が洗練されていきます。
さらに、行動を深く見つめ続けることで、その奥にある「Being(あり方)」への理解が自然と深まり、タレントアクティベーション(才能の発露)へとつながっていきます。私たちは、Doingを徹底的に追いかけるからこそ、その根っこにあるBeingを深く理解し、その育成へと繋げられると考えています。
OKRの先へ:「行動」が「組織」を動かす
「目標を達成する」だけではなく、「どのように達成するか」を明確にし、それを育て、フィードバックし、組織全体で共有していく。
そのプロセスの中で、社員一人ひとりの行動が磨かれ、組織は自律的に強くなっていきます。これは単なる目標管理の枠を超えた、新しいパフォーマンスマネジメントの姿です。
私たちは、OKRとコンピテンシーの統合こそが、企業が持続的な成長を遂げるための重要な鍵になると信じています。
次回のブログでは、そもそも「コンピテンシー」とは何かについて、もう少し深く掘り下げていきます。スーパーマンモデルと呼ばれる背景、項目分類やレベル、さらには行動結果面接(BEI面接)など、実践的な理解に役立つ観点を具体的に紹介していく予定です。
「自ら考え、行動し、成果を生み出す」組織の未来を、ともに築いていきましょう。