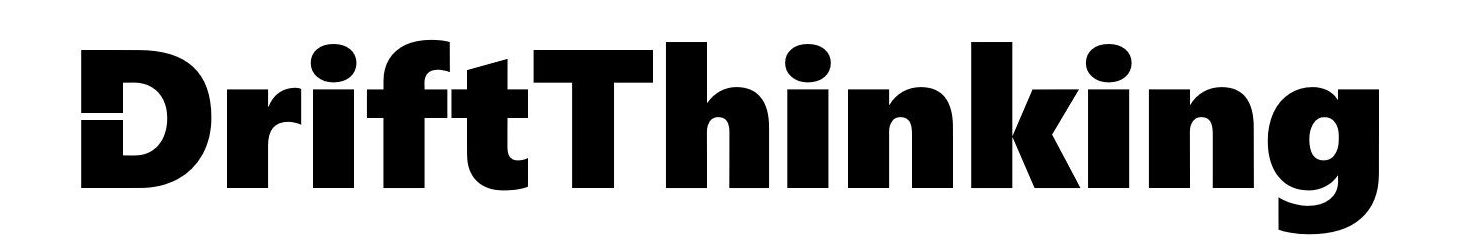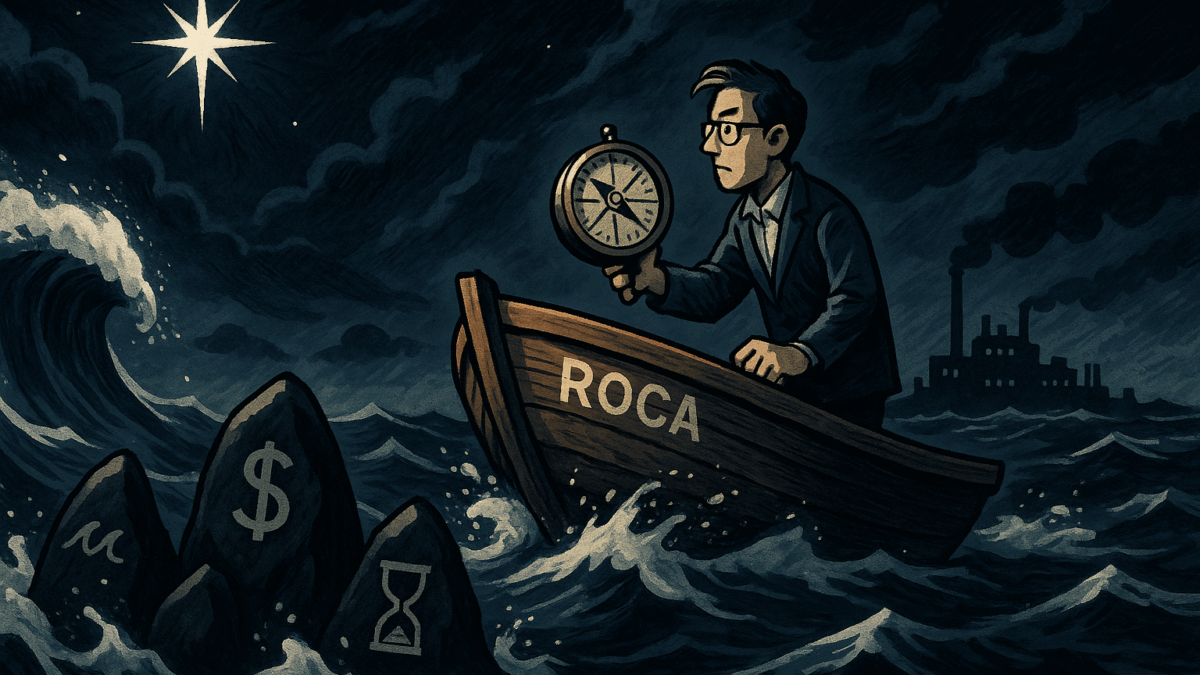スタートアップ経営は常に“霧の中の航海”です。とりわけピボット(大胆な方向転換)が必要な瞬間は、事業の命運が懸かる真夜中の荒波と言えます。本稿では、私が創業したROCAがろ過フィルター事業から酸化ガリウム半導体へ舵を切った実例をもとに、こうした局面でOKR(Objectives & Key Results)がどれほど強力な羅針盤になり得るかを解説します。
1. ROCAの挑戦:ろ過フィルターから半導体へ
ROCAは海水淡水化フィルターを開発する“水処理ベンチャー”として誕生しました。しかし市場検証の結果、1年足らずでPMF(Product Market Fit)の壁に直面。私たちは材料技術というコアコンピタンスを見極め、酸化ガリウム半導体へ大転換します。現在のFLOSFIAが保有する世界最小オン抵抗デバイスや大手企業との資本提携は、この決断なしには生まれませんでした。
2. なぜOKRが不可欠か
- アラインメント:Objectiveという“北極星”を掲げ、部門間のバラバラな優先順位を一瞬で整流。
- フォーカス:KRを3〜5個に絞り、限られた人・金・時間を一点突破に集約。
- トラッキング:週次の数字と行動ログで進捗を可視化し、遅延要因をリアルタイムで除去。
- エンゲージメント:自信度50%のチャレンジングな目標が“やらされ感”を“ワクワク”に変換。
3. ピボット検討期に置くべきOKR(例)
Objective: ろ過フィルター事業の課題を明確化し、PMFを達成する。
- KR1:顧客インタビューを通じて、PMF未達の原因を3点以上特定する。
- KR2:膜技術の応用可能性がある新市場を5つ以上リストアップし、評価軸を設定したうえで、選定完了する。(※選定完了とは事業計画に反映するところまで)
- KR3:選定した市場に対して、VCが認める実現可能性を示す結果・データを3点以上取得する。
4. ディープテック転換後のOKR(例)
Objective: 酸化ガリウム半導体技術の市場適合性とポテンシャルを示す。
- KR1:SBDを試作し、特性オン抵抗において世界最小記録を達成。(※SBD:ショットキーバリアダイオード)
- KR2:潜在顧客・デバイスメーカーへのインタビューを実施し、ニーズと技術課題の仮説を整理し、KPIを設定する。
- KR3:大手企業からの資本参画1件以上。
5. OKR設定の肝:4つの設計原則
2つの事例を見比べると、成果につながるOKRには共通する“型”があります。ROCAで私が学んだ設計原則を整理すると、次の4点に集約できます。
- ビジネス課題との“一対一”対応
Objectiveは「解決すべき最重要課題」を一句で言い切ります。KRはその課題が解けたかどうかを“客観データ”で証明する指標だけを置きます。事例①では「PMF未達の原因解明→新市場仮説→投資家の裏付け」という3ステップで課題を潰し込む設計、事例②では「技術ブレークスルー→顧客仮説→資本参画」の3点で市場適合性を検証する設計になっています。 - アウトカム ≠ アウトプット
KRは“やったかどうか”ではなく“結果が出たかどうか”を測ります。例②のKR1は「SBDを作る」ではなく「世界最小オン抵抗を達成する」。この違いがチームを技術ロマンではなく市場価値へ導きます。 - 先行指標 → 遅行指標の流れ
KRは ①学習系(先行)→②検証系(中間)→③回収系(遅行) の順に並べると、四半期のストーリーが一目瞭然になります。序盤で“霧を晴らす”学習系KRに集中し、仮説を掴んだら即検証。数字で手応えを示したうえで、資本参画や有償PoCなど回収系KRで成果を証明します。この三幕構成により「未知→検証→回収」というリスク低減プロセスをシンプルに語れます。 - 50%自信ルール
KRは「チームが本気でやれば50-60%は達成できる」水準に置くのがコツです。ハードすぎると諦め、イージーだと惰性が支配します。例①の“新市場5件→3件データ取得”、例②の“資本参画1件”は、ちょうど背伸びラインに設定しています。
6. Weekly Check‑in が未来を変える Check‑in が未来を変える
OKRの真価はWeekly Check‑inで開花します。15-30分の超短MTGで「Win/Blocker/Next Move」を共有し、KRを行動ベースで毎週更新。過去の棚卸しではなく“未来を設計する会話”にエネルギーを集中できます。
| 観点 | OKRなし | OKR+Check‑in |
|---|---|---|
| 目標共有 | 月末に結果報告 | 週次で再同期→ズレ即修正 |
| 学習速度 | 施策反映が遅い | Build‑Measure‑Learnが4倍速 |
| リソース配分 | サイロ化しがち | Blockerを横串サポートで即解消 |
| 人材成長 | 成果と能力が乖離 | 行動ログをコンピテンシー評価へ連携し、強みと伸び代を可視化 |
6. コンピテンシーとの連動
Weekly Check‑inで収集した行動データは、次回以降のブログで詳述するコンピテンシーモデルと接続します。KR達成に寄与した行動を指標化することで、
- 強みの言語化(組織全体でのナレッジ共有)
- 成長余地の特定(個別支援)
- 責任の分散(サポート範囲の明確化)
が可能になり、課題の可視化が進んで、組織は“機能する集団”へ進化します。
ピボットは「失敗の証」ではなく「戦略的成長のチャンス」です。OKRを北極星に、Weekly Check‑inをエンジンに、そしてコンピテンシー評価を軸受けに据えることで、組織は荒波を“条件”ではなく“優位性”へと転換できます。ROCAの物語があなたの次の一手のヒントになれば幸いです。