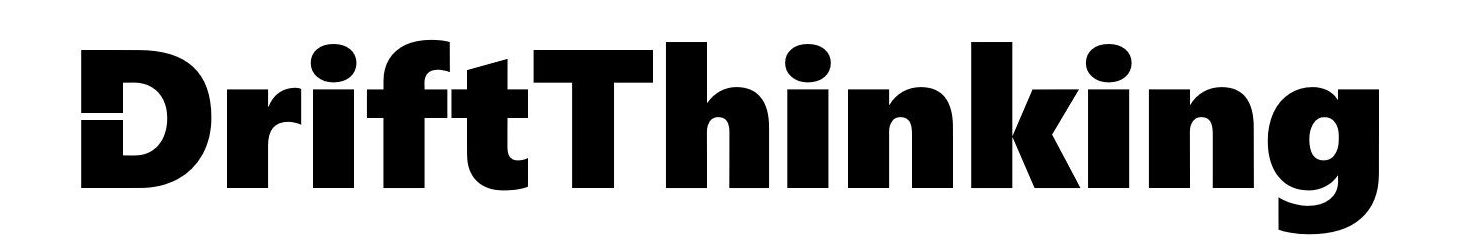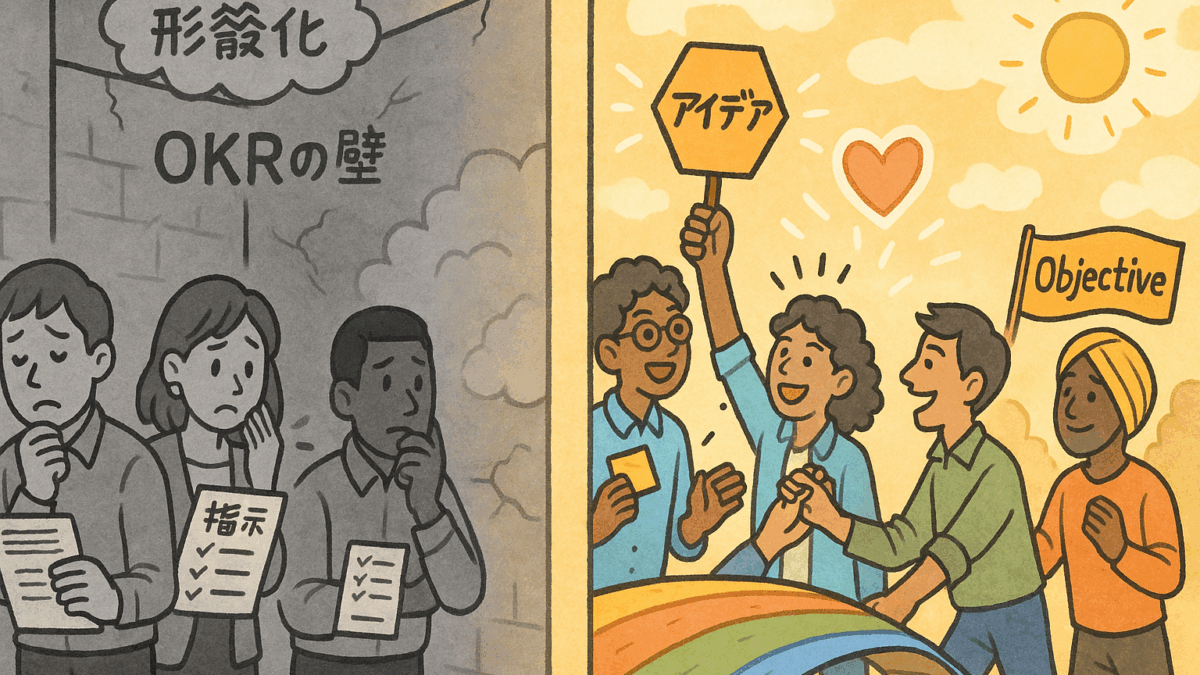OKR運用の“つまづき”とアライメント――“自分ごと化”と全体最適を両立するために
なぜOKRは続かない?――“形骸化”の壁にあるもの
OKRを導入した多くの組織やチームが、一度は悩む壁――
「最初は意欲的に始めたのに、だんだん続かなくなった」
「ObjectiveやKRが“作業リスト”や“お題目”になってしまう」
この“形骸化”はなぜ起きるのでしょうか?
ObjectiveとKRの“自分ごと化”が難しい理由
OKRの要は、「Objective(進みたい未来)」を自分やチームで本気で語れること、
そして、「Key Results(成果指標)」を“やらされ”でなく“自分ごと”として設定できることです。
しかし実際には、「会社や上司から下りてきた目標」だけを追いかけると当事者意識が薄れます。
一方で、“自分の本音”や“やりたいこと”だけでKRをつくってしまうと、全体の方向とズレてしまう――
この「自分ごと化」と「アライメント(全体最適)」のバランスが、現場では大きな悩みどころです。
OKRで求められる「アライメント」とは?
OKRは本来、「組織のビジョンや戦略(上位Objective)」と、「現場の個人やチームのやる気や工夫(ボトムアップKR)」をつなげる“接点”をつくるための手法です。
アライメントとは、全員が同じゴールを目指しながらも、それぞれの持ち場で“納得できる形”で貢献できる状態。「会社のため」だけではなく、「自分にとっても意味がある」「自分なりの挑戦ができる」と感じられることが、OKR成功のカギです。
KRの“半分はボトムアップ”――現場の知恵と裁量を活かす
実はOKR運用の現場では、KRの約半分は現場のメンバー自身が“ボトムアップ”で提案・設定することが推奨されています。
上位Objectiveをもとにしつつも、「この目標を達成するために、自分たちはどう貢献できるか?」「どんなやり方なら一番ワクワクできるか?」と自分たちで考え、KRを組み立てていく。これにより、上位のアライメント(全体方針)と、自分ごと(本音・裁量)の両方を実現できるのです。
“ズレ”を防ぐのは「対話」と「レビュー」
ObjectiveやKRが“ズレる”最大の原因は、設定したあとに上位と下位、組織と個人の意図がすり合わせされていないことです。
OKRは一度立てて終わりではありません。
定期的な対話――上位Objectiveとの関係、今のKRの意味・貢献度――を確認する「レビュー」が不可欠です。
たとえば、「このKRが上位Objectiveの実現にどう役立つのか」をチームで言葉にしてみたり、
週次の「チェックイン」で、進捗や迷い、軌道修正の必要性をオープンに話し合う場を設けましょう。
実践コツ:OKRの“納得感”を高めるために
- Objectiveは「自分ごと化」×「上位方針」両方を見つめて
- “上から降りてきたもの”に従うだけでなく、「自分が本当にやりたい/やれること」と「組織の目指す未来」の重なりを丁寧に探しましょう。
- KRは「成果」にこだわりつつ、“半分はボトムアップ”で提案する
- KRのいくつかは現場の自発的なチャレンジや工夫を反映させることで、意欲と創造性が高まります。
- 上位KRや全社KRと“つながる”説明ができるかどうかを意識。
- チェックイン&レビューを“習慣”に
- 毎週(または定期的に)OKRの進捗・課題・ズレを見直すことで、アライメントも自分ごとも「軌道修正」できます。
- このプロセスを「評価」ではなく「学びと進化」の場にすることで、プレッシャーや“やらされ感”が減ります。
まとめ:OKRは“自分ごと”と“全体最適”を両立する技術
OKRは、「本音」や「自分の納得感」を大切にしながら、組織の大きな目的と“つながる”ための仕組みです。
Objectiveを心から描き、KRの半分は現場からの声や知恵をボトムアップで加えつつ、定期的な対話で“全体最適”と“自分ごと化”の両方を育てていくという循環が、OKRを単なる“管理手法”から“現場で使える武器”に進化させます。
WithSTART™は、あなたの現場でOKRが根づくまで、対話と伴走を大切にサポートしていきます。
次回は、OKRの具体的な設定方法をテーマに、私自身が創業し、挑戦してきた仮想会社「ROCA」(FLOSFIA前身)のろ過フィルター事業からピボットに至った実話的なストーリーを用いて、
- その当時、OKRをどう設定していたら良かったか?
- どんなObjectiveやKRが考えられたか?
- 事業の方向転換(ピボット)時にOKRがどんな力を発揮するのか?
を実例ベースで分かりやすく紹介していきます。