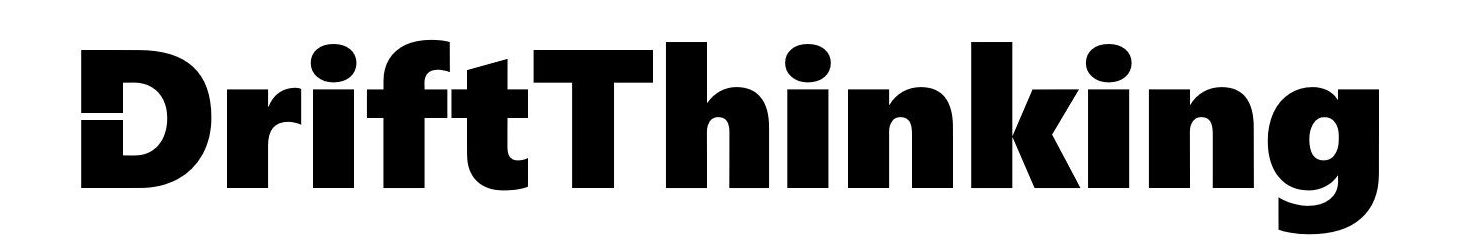「私はこういう人間だと思っていたけれど、本当は違うかもしれない」。
そんな風に、自分自身への見方がふと揺らぐ瞬間があります。
その揺らぎの奥に、私たちは“執着”という存在を見出します。
この連載の旅は、「見つめる」ことから始まります。
それは、自分の内面にそっと目を向け、今ここにある感情や感覚を受けとめる、静かな行為です。
“自分らしさ”という仮面の下に
「人に気を遣えるのが私らしい」
「ちゃんと努力するのが自分らしさだと思ってきた」
——こうした“らしさ”は、長年かけて身につけてきたものかもしれません。
けれど、その“らしさ”を守ろうとするあまり、
いつの間にか疲れていたり、苦しさを感じていたりすることもあるのではないでしょうか。
そこには、「こうでなければならない」という思い込み=執着が、
知らず知らずのうちに入り込んでいることがあります。
感情の奥にある「かたまり」に気づく
ドリフトシンキングでは、感情は「表層・中層・深層」という三層構造で捉えます。
- 表層:瞬間的に揺れ動く感情(苛立ち・焦り・喜びなど)
- 中層:日常の雰囲気に流れるような感情(違和感・期待・不安、自分には価値がないのではといった思い込みなど)
- 深層:安定的で根源的な感情(安心・慈愛・信頼・存在していてよいという感覚など)
たとえば、ささいな苛立ち(表層)の奥に、
「わかってもらえない」という違和感や「認められたい」という期待(中層)があり、
さらにそのさらに奥に、本来誰の内にもある「私はここにいていい」「私はすでに満たされている」という静かな感覚(深層)が眠っていることがあります。
「見つめる」とは、こうした内面の層の重なりに気づき、
それぞれを丁寧に感じとることなのです。
観察するだけで、なにかが動きはじめる
ここで重要なのは、「解決しよう」としないこと。
感情や執着を“直そう”とするのではなく、
ただ観察する、気づく、感じることが出発点になります。
たとえば、次のように問いかけてみてください。
- いま、自分のなかにどんな感情があるだろう?
- それは、身体のどこに感じている?
- どんな思考と結びついていそう?
こうした静かな観察によって、内面の「かたまり」は少しずつ緩みはじめます。
何かを変えようとしなくても、気づきによって自然に動き出す力が、私たちの中には備わっているのです。
「見つめる」だけで、漂いが始まることもある
しっかりと見つめることができれば、
そのまま自然に「眺め、離れる」感覚に至ることもあります。
つまり、「見つめる」ことは、すでに“漂う”ことの入口でもあるのです。
この連載では、さらに細やかに内面の変化をたどっていきますが、
実は最初のこのステップにこそ、最も大切な感性が詰まっています。
次回予告:「ほどく」へ
次回は、この「見つめる」行為によって見えてきた思考のパターンや価値観を、
どのように言語化し、やさしくほどいていけるかを探ります。
「なぜこんなにもこだわってしまうのか?」
その問いの先に、新しい理解の扉が待っています。