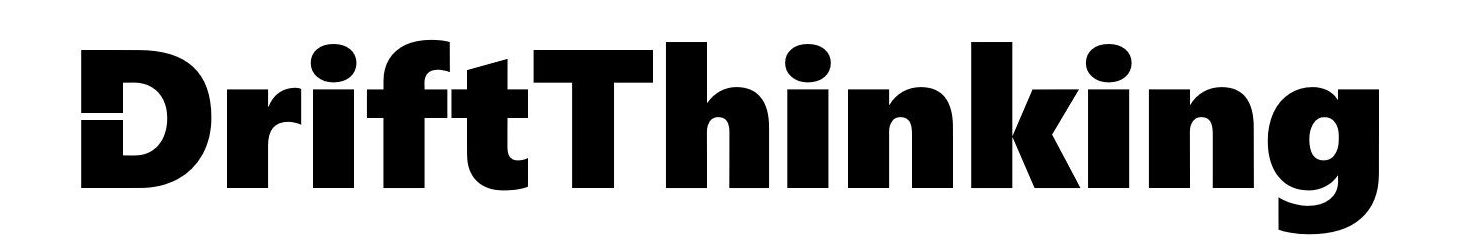これまで私たちは、ドリフトシンキングにおける「名づけ」という行為が、レトリック(修辞)の多様な技法と通じていることを見てきました。
比喩、換喩、提喩といった言葉の使い方を通じて、言葉にならない感情や感覚に形を与え、自己理解を深める過程をたどってきました。
けれど、ここで立ち止まって考えてみたいことがあります。
私たちはなぜ、そもそも「表現」しようとするのでしょうか?
そして、表現することで何が起こるのでしょうか?
ドリフトシンキングにおける表現の目的
ドリフトシンキングでは、内面をただ記録するのではなく、「名づける」ことによって、心の動きに新たな変化が起こることが重視されます。
たとえば、「心が固まっている感じがする」と書き出した瞬間、まるでその固まりが少し緩むように、感情が動き出すことがあります。
あるいは、「モヤモヤ」としか感じられなかった気分が、「焦り」と名づけられた途端、その原因や背景に目が向き、視野が広がるような感覚を覚えることもあります。
これは、言葉が単なるラベルではなく、思考と感情の流れを促す「媒体」になっていることを示しています。
表現することで、私たちは内面に働きかけ、感情の「定着」や「変化」を引き起こしているのです。
レトリックにおける表現の目的
一方、古典的なレトリックの目的は、しばしば「説得」とされます。
聞き手や読み手にある印象を与え、理解を促し、納得してもらう——そのために、比喩や語順、強調や省略など、さまざまな言葉の技法が用いられてきました。
けれど、説得だけがレトリックの目的ではありません。
佐藤信夫氏は、『レトリック感覚』の中で、レトリックが「ことばを通じて、見えにくいものを見えるようにする技術」だと説いています。
つまり、レトリックは人の認識を動かすための知的な工夫であり、ものごとの捉え方そのものを変化させる力を持っているのです。
共通する「変化を促す力」
ドリフトシンキングとレトリックは、一見まったく異なる分野に見えるかもしれません。
前者は自己観察や内面探求の技法であり、後者は対話や説得の技術です。
けれど、その根底には共通の目的があります。
それは、「言葉によって、認識を変え、変化を促す」こと。
ドリフトシンキングでは、自分の内面に名前を与えることで、今まで見えていなかった感情や思考の構造に気づきます。
レトリックでは、伝え方を工夫することで、聞き手や読み手の理解を深め、視点の転換をもたらします。
どちらも、言葉がきっかけとなって、見えなかったものが見えるようになる。
そして、その見え方の変化が、思考や行動、あるいは感情の流れに影響を及ぼすのです。
記述することで「自分が動く」
ドリフトシンキングの実践では、思考や感情を「エッセイ」のように書き出してみることが推奨されています。
このとき起こるのは、単なる記録ではなく、「記述することで自分が動く」という体験です。
言葉にすることで、モヤモヤが形になり、その形がさらに新たな問いを生み出す。
結果として、自分自身へのまなざしが変わり、そこから行動や選択にも変化が生まれる——。
このようなプロセスは、レトリックが持つ「影響を与える技術」との共鳴でもあります。
表現は、自己理解と発見の装置
私たちが日常で何気なく使っている表現にも、こうした変化のきっかけが潜んでいます。
- 「何かが引っかかってる気がする」
- 「うまく飲み込めない話だった」
- 「これは腑に落ちない」
これらは、身体感覚と感情を組み合わせたレトリック的な表現でありながら、自己の状態に気づくための装置として機能しています。
日常の言葉に目を向けることで、私たちは自分でも気づいていなかった内面にアクセスできるようになるのです。
そしてそれは、ほんの一言であっても、心のあり方をやさしく揺らす力を持っています。
次回はいよいよ最終回です。ここまでの内容をまとめながら、ドリフトシンキングにおける内面表現の可能性、そして日々の生活での実践ヒントをお届けします。
内面への「名づけ」は終わりのない旅ですが、その旅の中には、自分だけの言葉で世界を見つめ直す楽しさが待っているかもしれません。