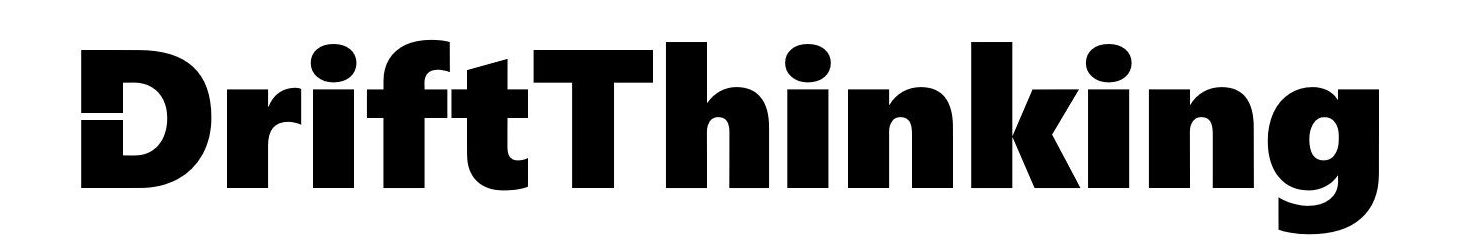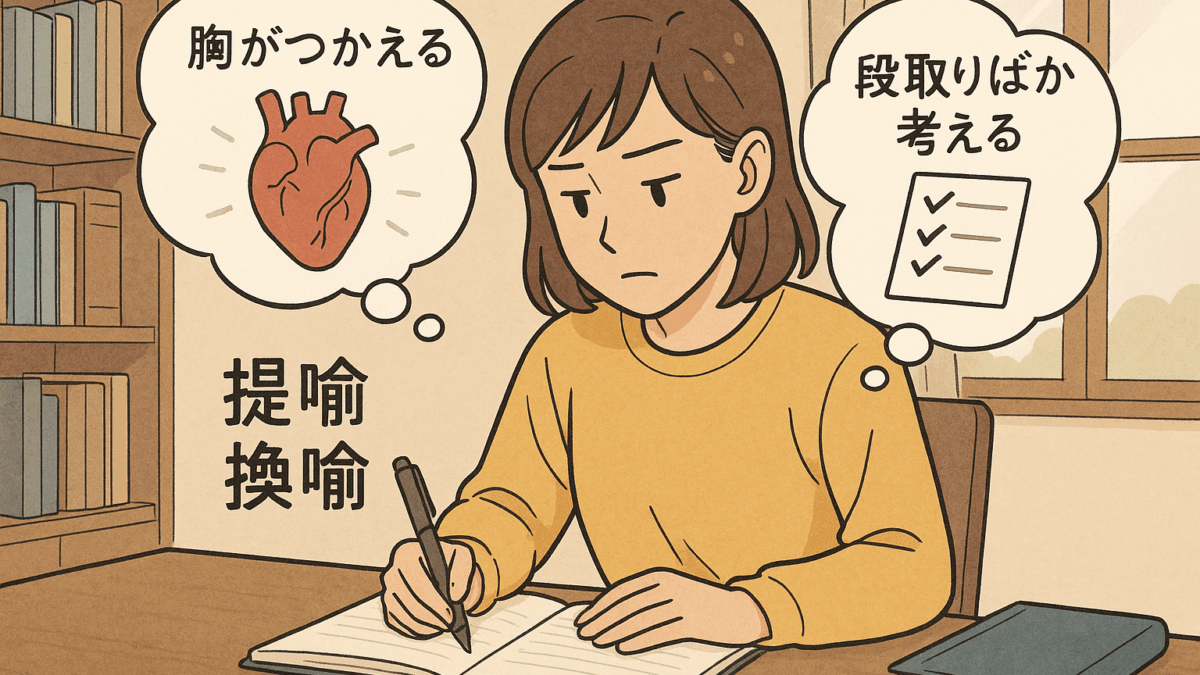これまでの回では、内面を「名づける」プロセスにおいて、比喩が果たす役割に注目してきました。
けれど、言葉の技法は比喩だけではありません。私たちが自分の感情や感覚を表現する際には、意識しないまま、さまざまなレトリックの技術を使っています。
今回は、「換喩(メトニミー)」や「提喩(シネクドキ)」といった比喩以外の表現技法に着目し、それがドリフトシンキングにおける「名づけ」とどのように関わっているのかを探っていきます。
内面を言葉にするとき、私たちは何を使っているか
たとえば、ある人が「胸がつかえる感じがする」と表現したとき、それは「不安」や「後悔」といった抽象的な感情を、身体の感覚に置き換えて言語化していることになります。
このとき使われているのが、レトリックでいう「換喩」の技法です。
換喩とは、あるものを、それと密接な関係にある別のもので表すこと。原因や結果、道具や場所など、直接的ではないけれど密接に関連する何かを通して、伝えたい内容を浮かび上がらせる技法です。
換喩:身体感覚を通して感情を表す
ドリフトシンキングでは、「感情を身体の反応としてとらえる」場面がよく見られます。
たとえば:
- 「胸のあたりが締めつけられる感じがした」
- 「背中がぞわっとする」
- 「胃のあたりに重さがある」
これらはすべて、心理状態を身体の感覚に置き換えて表現する、換喩的な記述です。
それによって、感情そのものが言葉にならずとも、感情に「輪郭」を与えることができます。
また、身体感覚の描写は、主観的な体験を共有可能なイメージに変換する役割も果たします。
「悲しみ」よりも、「喉の奥がじわっと熱くなる」と表現された方が、読んだ人は共感しやすいのです。
提喩:一部で全体をあらわす
もう一つの技法「提喩」は、全体をその一部で、あるいは部分をその全体で表現する方法です。
たとえば、「私はいつも段取りばかり考えている」という表現には、「段取り」という行動の一部で、思考全体の習性を言い表す提喩的な構造が含まれています。
また、「いつも眉間にしわが寄っている自分がいる」という記述は、「眉間のしわ」という身体的な一部の表現を通して、全体としての心理状態を示しているとも言えます。
提喩は、ドリフトシンキングの中でも、日々の習慣や思考パターン、繰り返される行動の中から内面を言語化するときに頻出します。
一部に注目することで、無意識のうちに繰り返されている内的構造に気づくことができるのです。
なぜ比喩だけでは足りないのか
比喩は強力な表現手段ですが、感情や思考のすべてを「何かにたとえる」だけでは捉えきれないこともあります。
内面はもっと多層的で、日常的な言葉や行動、身体の感覚の中に埋め込まれた状態として現れるからです。
換喩や提喩は、そうした「文脈の中の内面」を表すのに適しています。
「朝になると胃が重くなる」「連絡が返ってこないと、いつも手が震える」——こうした表現は、生活の中に染み込んでいる感情や不安を言語化する助けになります。
つまり、多様なレトリックの技法を使い分けることで、より精度の高い、そして多角的な内面の記述が可能になるのです。
名づけは「発想」でもある
古典レトリックでは、表現技術の第一段階を「発想(invention)」と呼びます。
何を語るか、どんな内容を伝えるかを見つけるフェーズです。
ドリフトシンキングでの「名づけ」も、まさにこの発想の段階にあたります。
まだ言葉になっていない感情や感覚を、どの視点から、どの言葉で表現するかを見つける。その行為そのものが、思考の起点となり、自己理解の入り口になるのです。
自分の内面を、多様な言葉で捉える
比喩、換喩、提喩——それぞれの技法には、それぞれに向いている表現があります。
感じていることが身体感覚として現れているなら、換喩が有効かもしれません。行動の癖や思考パターンをとらえたいなら、提喩が役立つでしょう。
そして、これらの技法を意識することで、「自分の言葉の使い方」に対する感覚も研ぎ澄まされていきます。
それは、佐藤信夫氏が『レトリック感覚』で述べたように、「ことばそのものを感じる力」として、私たちの表現をより豊かなものにしてくれます。
次回は、こうした言葉の技術が、単なる表現にとどまらず、「自己を変化させる力」として働くことについて掘り下げます。
表現することが、なぜ心を動かすのか? そして、それがどのように私たちの内面の理解や行動に影響するのか。
レトリックとドリフトシンキングの共通点が、より深いレベルで見えてくるはずです。