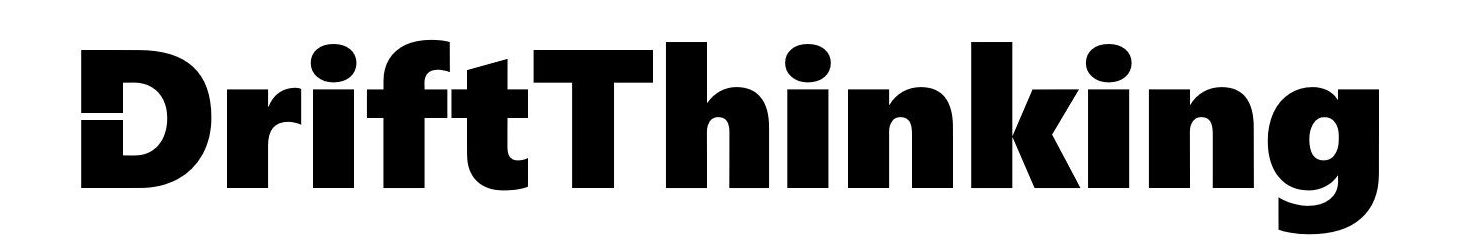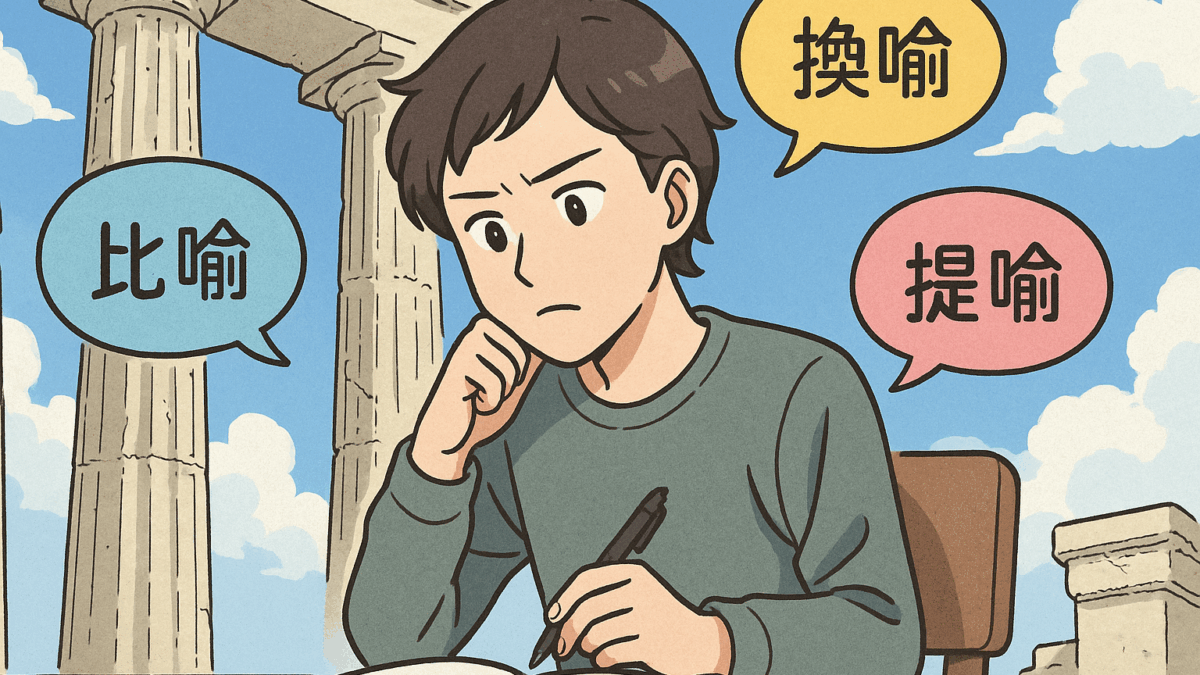前回の記事では、ドリフトシンキングの実践において、自分の内面に「名前をつける」ことが、自己理解と発見に繋がることを紹介しました。この「名づけ」は感覚的な行為のようでいて、実は古代から研究されてきたある言葉の技術とも深く関係しています。
その技術とは、「レトリック(修辞)」です。
レトリックとは、何のための技術か
「レトリック」という言葉に、どんな印象を持つでしょうか?
うわべだけを飾る言い回し、言い逃れのテクニック、あるいは政治家の演説で使われるごまかしの道具——そのような負のイメージを持つ人も少なくありません。
しかし、本来のレトリックは、もっと広く、そして奥深い技術です。
言葉を使って、感じたこと、考えたことを他者にわかりやすく、印象深く伝える。そのための「言葉の工夫の体系」がレトリックです。紀元前のギリシャ・ローマ時代には、弁論術として政治・司法の現場で重視され、やがて詩や文学、哲学にも影響を与える普遍的な表現技術として発展していきました。
レトリックの五つの基本構成
古典的なレトリックは、以下の五つのプロセスに分かれるとされています:
- 発想(invention):伝えるべき内容を見つける
- 配置(disposition):それをどう構成するか
- 修辞(style):どんな言葉づかいで表現するか
- 記憶(memory):それをどう覚え、思い出すか
- 発表(delivery):どう伝えるか(声、態度などを含む)
この中でも特に、私たちのテーマと関係が深いのが「修辞(style)」の部分です。
「言葉のあや」──修辞の核にある比喩の力
修辞の中心的な技法には、「比喩(メタファー)」や「直喩(シミリー)」といった、言葉の置き換え・例えの技術があります。
これらは、抽象的で把握しにくいものを、より具体的で共有しやすいかたちにするための方法です。
たとえば、「焦り」という感情をそのまま「焦り」と言っても、相手には伝わらないかもしれません。
しかし「胸の中で細かい火花が散っているよう」と表現すれば、相手はその状態を視覚的に、身体感覚的にイメージできます。
このように、比喩表現は、ただ美しいだけではなく、「伝わる」「共有される」ための工夫です。
そして、これはまさにドリフトシンキングで内面を記録するとき、私たちが無意識のうちに使っている方法でもあります。
『レトリック感覚』が教えてくれること
佐藤信夫氏の著書『レトリック感覚』では、レトリックは「表現しにくい現実をどう伝えるか」の試みであると語られています。
つまり、レトリックとは、人間の不完全な認識や混沌とした感情に、何とか言葉を与えていこうとする営みなのです。
その中で重要なのが、「類似性」や「意外性」を発見し、それを言葉にする感覚です。たとえば、ある悲しみが「雨に濡れた図書館のようだ」と表現されたとき、そこには比喩だけでなく、感覚的な共鳴と、意外な視点の転換があります。
こうした表現が生まれるとき、私たちは単に感情を伝えているだけでなく、自分自身の内面を新たに発見し直しているのです。
レトリックは、誰にでも開かれた技術
レトリックというと、文学や演説、専門的な知識を連想しがちですが、実はこれは私たちの日常会話にも自然と含まれている技術です。
たとえば、
- 「頭が真っ白になる」
- 「心にぽっかり穴があく」
- 「のど元まで言葉が出かかっている」
こうした表現はすべて、身体感覚や空間のイメージを通して、内面を共有しようとするレトリックの一種です。
つまりレトリックとは、誰もがすでに使っている「日常の言葉の技術」なのです。
そして、それを少しだけ意識的に使ってみることで、私たちはもっと豊かに、自分の内面と向き合い、他者と分かち合うことができるようになります。
次回は、このレトリックの中でも特に重要な「比喩」の技法に焦点を当て、ドリフトシンキングの実践とどのように重なり合っているのかを見ていきます。
あなたの中にまだ言葉になっていない気持ちや感覚。それを比喩というレンズを通して見つめ直すことで、どんな発見があるでしょうか。
ぜひ次回もご期待ください。