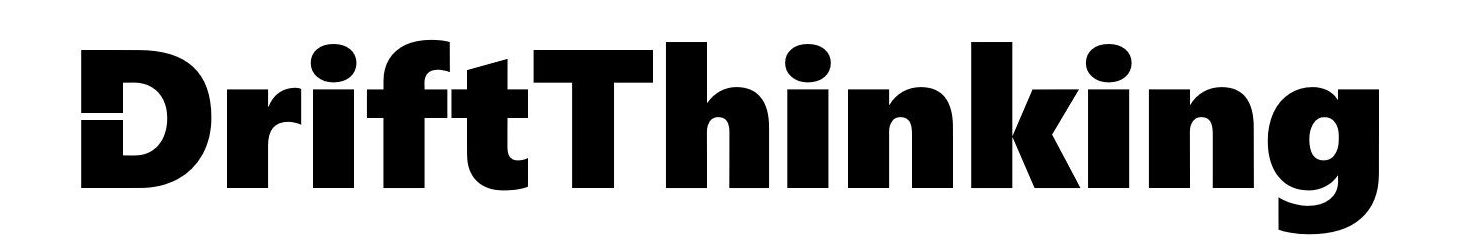日々の生活のなかで、私たちはさまざまな感情や思考、身体の感覚を経験しています。しかし、それらの多くは明確な言葉にならず、曖昧なまま心の奥にとどまります。「なぜかモヤモヤする」「うまく説明できない」——そうした状態が積み重なると、自分自身の内面が見えづらくなり、他者との関係にも小さなずれが生まれてきます。
このブログシリーズ『名づけでひらく自己理解──言葉にすることで見えてくるもの』では、そうした「言葉になりにくい内面」を丁寧に見つめる思考技術「ドリフトシンキング」と、言葉による表現の知恵「レトリック(修辞)」を軸に、自己理解と表現の可能性を探っていきます。
自分の感情や思考に、ことばで「かたち」を与える
ドリフトシンキングは、感情・感覚・思考といった内面の動きに注意を向け、無理に整理せず、まずは「感じること」「気づくこと」を重視します。そのうえで、自分なりの言葉や色、音、記号などを使って、それらに名前をつけて記録していきます。
この「名づけ」の工程は、曖昧だった内面に「かたち」を与え、可視化していく試みです。そしてこれは、自己理解のためだけでなく、他者との間で「共有可能な言葉」を探す行為でもあります。
『レトリック感覚』が教えてくれる、表現の奥行き
このシリーズを構想する際、私自身が強く影響を受けたのが、佐藤信夫氏の著書『レトリック感覚』です。そこでは、「レトリック」とは単なる言葉遊びや美文のテクニックではなく、「表現しにくい現実をどうとらえ、どう表現し、どう共有するか」という深い問いに応える技術として描かれています。
たとえば、抽象的な感情を「重たい石のよう」「じんわりと染み出す霧のよう」と表現する比喩の力。それは単に例えているのではなく、自分と他人の感覚のずれを橋渡しし、理解しあうための工夫です。そしてその工夫が、人生のなかの小さな発見や、思わぬ豊かさをもたらす——これが『レトリック感覚』の魅力であり、本シリーズが目指す方向でもあります。
全6回の構成と主なテーマ
このシリーズでは、以下の6つのテーマを通じて、ドリフトシンキングとレトリックの交差点を探っていきます:
- 言葉にならない内面に光を当てる──ドリフトシンキング「名づけ」の役割
- 表現の技術「レトリック」の多様な世界
- 内面を「例える」技術──ドリフトシンキングと比喩表現
- 比喩だけじゃない──内面表現と他のレトリック技法
- 表現することの「力」──内面理解とレトリックの目的
- 内面表現の冒険へ──まとめと実践への誘い
言葉で考えることは、見えないものに光を当てること
このシリーズでは、ことばを「発見の道具」として使いながら、内面を静かに探る視点を提示していきます。
名づけ、比喩、記録、表現——それらを通して、自分自身の心の輪郭が少しずつ見えてくる。その過程は、佐藤信夫氏が描いたように、「ことばのあや」によって私たちの現実認識が深まるプロセスと重なります。
あなた自身の「まだ名前のない思い」に、ことばを与えてみたくなったとき——このシリーズがその一助となれば幸いです。次回から、具体的なテーマごとに、内面と言葉の関係を解き明かしていきます。