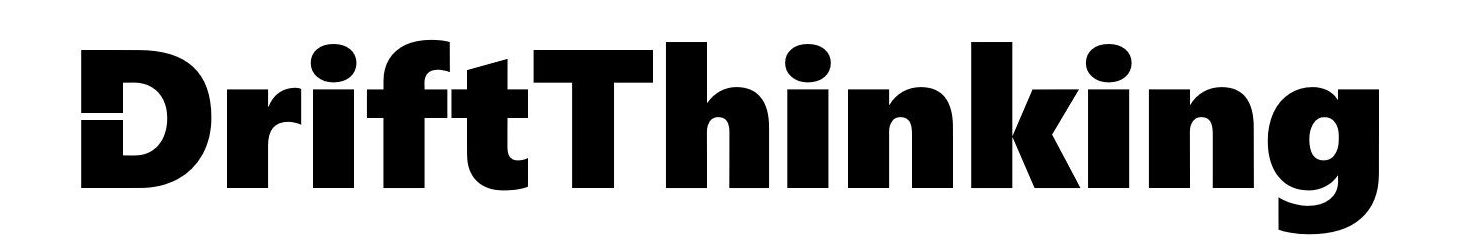職場や教育の現場で、私たちはこれまで「フィードバック」や「フィードフォワード」といった方法を通じて人を支援してきました。フィードバックは過去の行動や成果を振り返り、評価や助言を与えるもの。フィードフォワードは、未来に向けた希望や方向性を先に提示し、その実現に向けた行動を促す手法です。
いずれも有効な方法ですが、そこにはある前提が存在します。それは「支援する側が正しい認識を持ち、支援される側はまだそれに到達していない」という暗黙の関係性です。この関係に立脚する限り、支援とは“指導”であり、“導き手”が“受け手”に向けて一方的に働きかける構造が維持されます。
しかし本当に、支援する側が常に正しいとは限らないのではないでしょうか。当事者自身の内面にも、未だ言葉になっていない大切な気づきや感覚が眠っているかもしれない。そんな視点から、「DriftThinking™」の姿勢を取り入れた新しい支援のあり方として、私たちは「FeedDrift(フィード・ドリフト)」を提唱します。
FeedDriftでは、支援者の役割が大きく変わります。評価を与える人、正解を示す人ではなく、当事者の内面に寄り添い、その人自身が本当の気持ちや感覚に気づいていくプロセスを静かに見守る人になるのです。
たとえば、ある社員がプロジェクトの報告をしながら、何となく浮かない表情をしていたとします。そのときにFeedDriftの視点を持つ先輩は、「なぜ元気がないのか」「どこが問題なのか」と問い詰めることはしません。むしろ、「今の取り組み、あなたらしさはどう感じている?」と静かに問いかけ、本人が自分の感情や感覚に耳を傾けるきっかけをつくります。
このときのポイントは、判断を急がないこと。成功だったのか失敗だったのかを決めつけるのではなく、そのとき心に浮かんだ違和感や迷いを、そのまま大切に扱うことです。そして、それを無理に整理したり克服しようとはせず、変化していくプロセスを丁寧に味わうように支援します。
このようなアプローチを重ねていくことで、当事者は少しずつ、自分自身の本音や願いに気づいていきます。「実はこのプロジェクト、周囲の期待に応えようとしていただけで、自分にとって本当に大切なものではなかった」「もっと自分らしい関わり方があるかもしれない」といった気づきが芽生えることもあるのです。
組織にとっては、こうした内省のプロセスが離脱や意欲低下につながるのではと懸念されるかもしれません。しかし実際には、内面と向き合い、自分の意思で取り組むことを選び直した人は、むしろいっそう主体的で持続的な貢献を始める傾向が強くなります。
FeedDriftの支援は、すぐに答えを出すことを求めません。急がず、寄り添い、本人の「内なる推進力」が自然と動き出すのを信じて待つ。これは、効率性が求められる現代社会において、いささか遠回りに見えるかもしれません。しかし、深い納得感に裏打ちされた自発的な行動こそが、最も強く持続的な力となるのです。
FeedDriftは、支援とは「導くこと」ではなく、「気づきを見守ること」だという発想の転換を促します。そしてこの静かな変化こそが、個人と組織のより豊かな成長を支える新しい支援のかたちなのです。