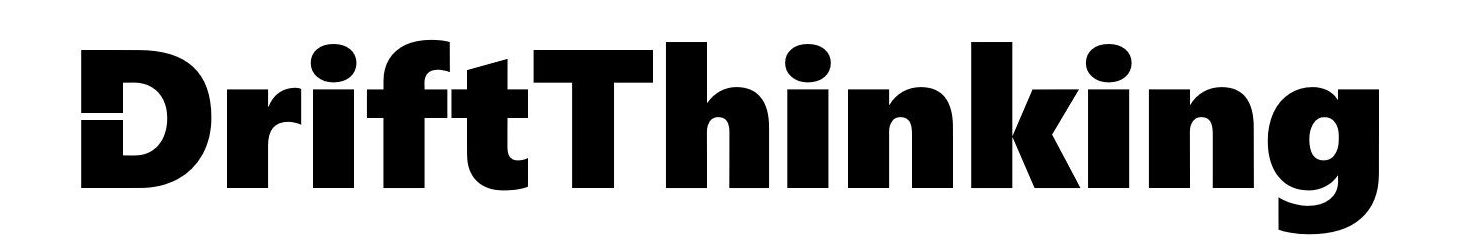私たちは日々、考え、判断し、行動しています。
その背景には、感情や感覚、そして思考の「クセ」があります。
「なぜかいつも同じことで反応してしまう」
「つい人に合わせてしまう」
「本音を言いたいのに言えない」
──そんな“無意識の反応”には、自分でも気づいていない思考のパターンや前提が隠れています。
ドリフトシンキング(DriftThinking™)は、そうした内面の動きを静かに観察する、新しい実践アプローチです。
感情や感覚、価値観、思考、習性といった“自分の内側”にやさしく意識を向けることで、いつもの反応に流されず、内側から湧き上がる願いに気づき、新しい選択肢を生み出します。
自分の問いから始める、理論との関わり方
自己成長のために、心理学やコーチング理論など、さまざまな知見に触れる機会があります。
その中でも成人発達理論は、「人は大人になってからも、ものの見方や意味づけの構造が発達し続ける」という前提に立ち、反応や判断の背後にある“認識の構造”に目を向けることを促します。
この理論は、ロバート・キーガンやスザンヌ・クック=グロイターらの研究を背景に、人が成長とともに「他者の期待に合わせる段階」から「自分の信念に基づいて生きる段階」、そして「多様な視点を統合する段階」へと変化していくプロセスを示しています。
ただし、ここで注意が必要なのは、この理論を「〜でなければならない」という外的な評価軸として使わないことです。
DriftThinking™が大切にするのは、「なぜ今、自分はこの理論に惹かれたのか?」という内側の問いに立ち返ること。
自分の言葉で、経験を通して理解していく姿勢です。
クライアントが求める理論だからこそ
DriftThinking™で成人発達理論を取り入れるのは、あるクライアントがその理論に関心を寄せたとき。
求めているのがクライアント自身だからこそ、その背景にある動機や文脈を大切にしながら、その人が自分のペースで試せるように、補助線としてそっと添えたいと考えています。
理論は「正解」ではなく、「問い」として使う。
その関わり方こそが、内側からの納得や変化を育てる鍵になるのです。
DriftThinking™が成人発達理論を取り入れるときの3つの視点
DriftThinking™では、成人発達理論のような枠組みを「外から押し付ける正解」としてではなく、「自分の内面を観察するための補助線」として活かします。
この理論の持つ構造的な示唆は、以下の3つの視点から活用することで、より深い気づきへとつながっていきます。
1|“気づき”を深めるレンズとして使う
成人発達理論は、私たちがどのような構造で物事を意味づけているのかに注目します。
たとえば、「他者に合わせてしまう反応」が、どんな前提や恐れから来ているのか──
そうした内面の“構造”に気づくことで、感情や反応をより精緻に観察することができます。
2|思考に“意味”を与える言葉になる
繰り返される思考のクセや反応を、単なる「弱さ」や「未熟さ」として見るのではなく、発達段階に応じた傾向として捉える視点が得られます。
「これはいまの自分の構造に由来する自然な反応かもしれない」と理解できることで、自己否定ではなく、やさしい観察へと変わっていきます。
3|新しい行動を“仮説”として試す土台になる
成人発達理論が示す、より高次の認識や行動は、DriftThinking™において「試すべき正解」ではなく、「やってみたらどうなるか?」という仮説としての実験対象です。
「信念を表現してみる」「他者の視点を統合してみる」といった行動を、少しずつ日常の中で試してみることが、新たな理解と変化を育てていきます。
理論を内面化するプロセス──守破離としてのDriftThinking™
DriftThinking™では、知識や理論をただ“知る”のではなく、自分の内面に引き寄せて試しながら、自分なりに理解していくことを大切にしています。
そのプロセスは、日本的な学びの概念である「守破離(しゅはり)」に通じています。
- 守|まずは素直に取り入れてみる
- 破|自分の観察と対話を通じて、違和感やズレを検証する
- 離|自分なりの形で、自然な在り方や振る舞いを見つけていく
このようにして、理論を「正解」ではなく、「仮説」や「問い」として柔らかく扱う。
それが、DriftThinking™が目指す自己成長のあり方です。
結びに
思考のクセに気づき、その起点を問い直すことは、Being(在り方)に立ち返ること。
そこから新しいDoing(行動)を試し、また観察する──
この静かな循環が、内面から確かな変化を育てていきます。
DriftThinking™は、あなたの中にあるまだ言葉になっていない問いに、静かに寄り添い、支える存在でありたいと考えています。