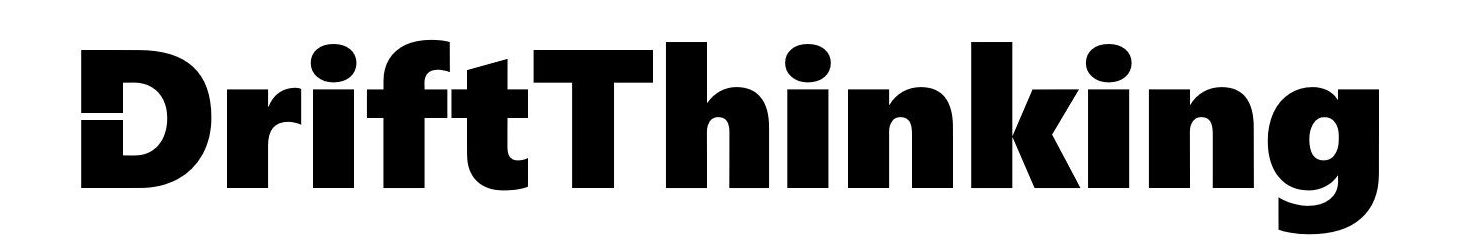私たちの内面には、一人ひとり異なる「色彩」があります。
それは、感情、感覚、価値観や思考のクセなどが織りなす、静かで複雑な風景です。
ドリフトシンキングは、その風景をやさしく探求していくためのアプローチです。
この探求は、何かを“分析する”というよりも、「感じる」「気づく」ことから始まります。
日々変化する内面の動きに静かに耳を澄ませ、その背後にある思考や感覚、価値観のパターンに丁寧に目を向けていく――それがドリフトシンキングの基本姿勢です。
外側ではなく、内面そのものに目を向ける
感情が生まれると、私たちはつい「何があったか(=外の出来事)」に意識を向けてしまいがちです。
しかしドリフトシンキングでは、感情の引き金となった出来事よりも、「感情がどのように生まれ、どのように動いたのか」に意識を向けます。
たとえば、「不安」という感情を感じたとき、その奥には「失敗してはいけない」「評価されるべきだ」といった思考があり、同時に胸の圧迫感や腹部の緊張など身体の感覚が伴っていることに気づくことがあります。
このように、ドリフトシンキングでは感情・感覚・思考という内面の動きそのものに注目し、自分自身の反応パターンを静かに見つめていきます。
思考スタイルという「個性」
こうした内面の動きは人によってまったく異なり、それが「個性」として現れます。
とくに注目したいのが、情報の捉え方・処理の仕方に現れる思考スタイルの違いです。
テンプル・グランディン著『ビジュアル・シンカーの脳――絵で考える、言葉でとらえる』(NHK出版)では、人間の思考スタイルを次のように分類しています。
- 言語思考型:言葉をベースに物事を理解し、記憶し、論理的に整理する傾向のある人
- 視覚思考型(ビジュアル・シンカー):頭の中でイメージを詳細に描き、図や映像を使って考えるのが得意な人
多くの人はこのスペクトラムのどこかに位置しており、両方のスタイルを混ぜ合わせた「混合型」である場合も多いとされています。
たとえば、家具の組み立て説明書を見るとき、言語思考型の人は文章説明を丁寧に読みますが、ビジュアル・シンカーは図解を一目見ただけで全体像を掴みやすいと感じます。
ビジュアル・シンカーにとっては、言葉では表現しきれない豊かな内面が、イメージによって初めて整理され、理解可能になるのです。
自然な表現スタイルを使う
ドリフトシンキングでは、内面に浮かんだ感情や感覚、思考に対して、「言葉」や「イメージ」で丁寧に表現することを推奨しています。
この表現方法は、思考スタイルに応じて柔軟に選べるべきものです。
たとえば:
- 言葉がしっくりくる人は、文章で気づきを書き出す
- イメージ派の人は、図、スケッチ、記号で構造的に捉えてみる
- 曖昧な感覚しか掴めないときは、「よくわからない」とそのまま残しておく
というように、自分にとって自然な方法で表現することで、内面の動きがより明確になり、自己理解が深まっていきます。
個性を味わいながら進む、静かな旅
このように、ドリフトシンキングは画一的なやり方を押しつけるものではなく、「自分らしい方法」で内面を観察し、表現することを大切にします。
何かを“理解しよう”と焦る必要はありません。
ただ感じること、気づくこと、そのプロセスそのものが、自己理解の旅の本質だからです。
「よく分からない」という状態にも、必ず意味があります。
そしてそれを繰り返し味わうなかで、無意識の思考パターンや内面の“色合い”が少しずつ見えてくるでしょう。
まとめ
ドリフトシンキングは、視覚派の人も、言語派の人も、それぞれが自分に合ったスタイルで内面と対話できる柔らかなフレームです。
このプロセスを通して、誰もが自分自身の「静かな個性」と出会い、受け入れ、育んでいくことができます。
あなたの中に眠る、まだ言葉にもイメージにもなっていない“色彩”を、ゆっくりと見つけに行きませんか。