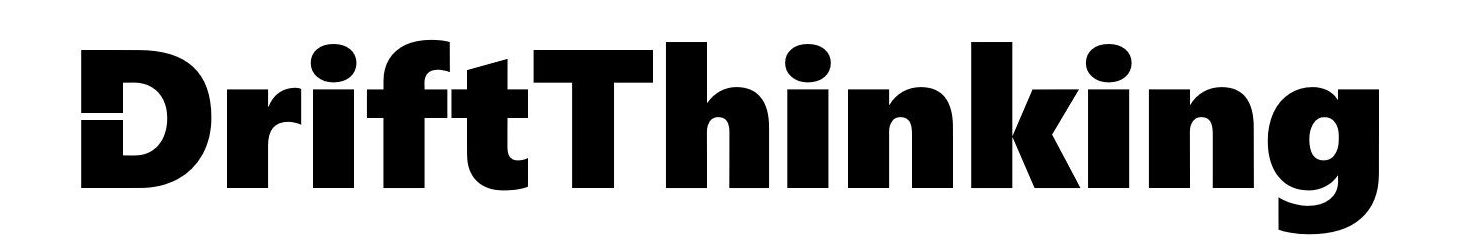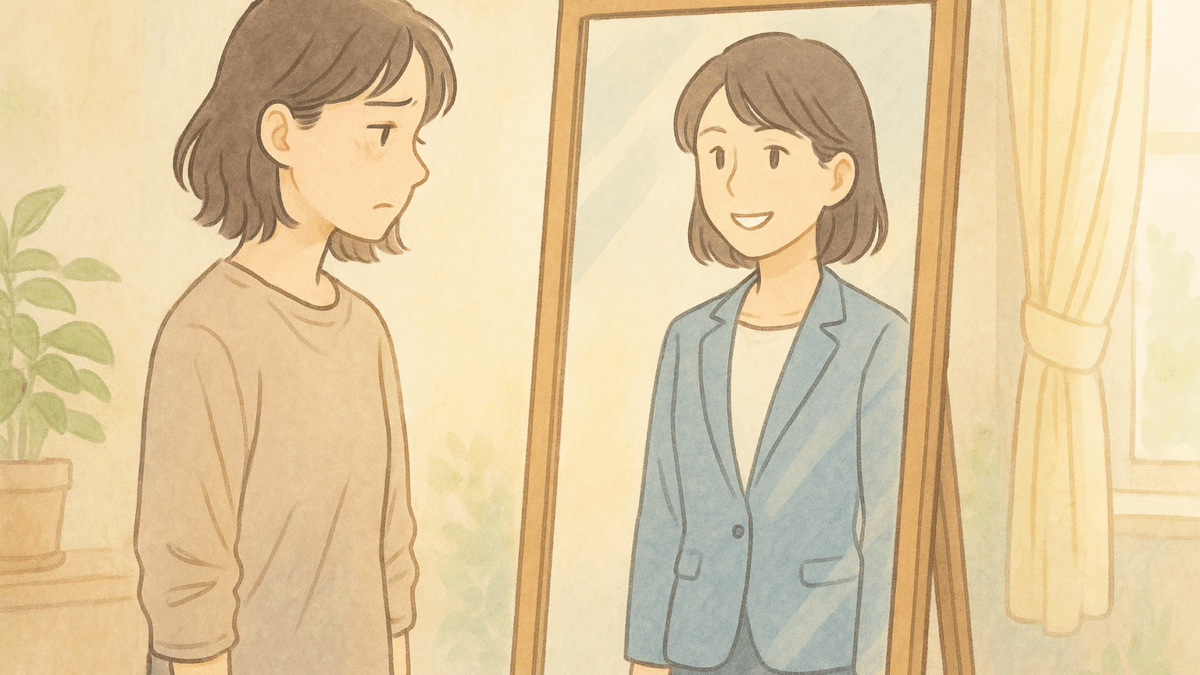前回は、思考や執着をほどいたときに生まれる「揺れ」について見つめました。
その揺れは、ただの迷いではなく、内面が新しい方向に動き出しているサインでした。
けれど、揺れを感じたとき、私たちはすぐに「こんな自分ではダメだ」と否定したくなることがあります。
そこには、知らず知らずのうちに築き上げてきた「理想の自分」という影が横たわっています。
「こうありたい」の奥にあるもの
「きちんとしていたい」
「誰かの期待に応えたい」
「弱さを見せたくない」
——そんな思いは、日常の中で私たちを動かす原動力にもなっています。
でもそれが、「そうでなければ、自分には価値がない」という思いと結びついたとき、
その理想は自分を縛るものへと変わっていきます。
「ゆるす」という行為は、こうした理想との関係を問い直すためのステップです。
ゆるすとは、「いまの自分」をそのままにしておけること
「ゆるす」という言葉には、“許可を与える”という響きがあります。
でもここでの「ゆるす」は、何かを許可するというよりも、
「そのままにしておく」ことを許容するというニュアンスに近いのです。
- 揺れている自分を、そのままにしておく
- 思い通りにできない自分を、ただ見守る
- 理想通りに進めない状況に、抗わずにいる
それは、自分を甘やかすことではなく、
自分とのあいだに余白をつくる行為です。
理想は消さなくていい
大切なのは、理想を「なかったことにしよう」とするのではなく、
理想と向き合いながらも、それに縛られすぎない感性を育てることです。
「ちゃんとしたい」という思いは、きっと大切にしてきた価値観の一部でしょう。
だからこそ、完全に手放すのではなく、
「いまはまだそこに届かなくてもいい」と思える柔らかさを持つこと。
その柔らかさが、「漂う」感性の種になります。
自己否定の声との付き合い方
揺れているときほど、「こんな自分ではダメだ」という声が強まります。
その声を無理に消そうとせず、ただその存在を認識して、
こう問いかけてみてください。
- それは、誰の声に似ているだろう?
- いつ頃から、そう思うようになったのだろう?
- 本当にいまの自分に必要な声だろうか?
この問いは、「赦す」準備を整えるための静かな対話です。
自分の中の理想と現実に橋をかける作業でもあります。
ゆるしの先に現れる自由
「ちゃんとできない自分」「揺れている自分」をそのままにしておけると、
そこに少しずつ、動ける感覚や、試してみようと思える自由が戻ってきます。
理想にぴったり合った自分ではなくても、
いまの自分で一歩踏み出せるようになる。
その自由さは、次のステップ「遊ぶ」につながっていきます。
次回予告:「遊ぶ」へ
次回は、「自分らしさ」に新しい余白が生まれたあと、
それをどう活かしていくか、どう“遊ぶ”ように使い直していくかを探ります。
ゆるんだ感性の先にある、創造的で軽やかな自分との出会いをお楽しみに。