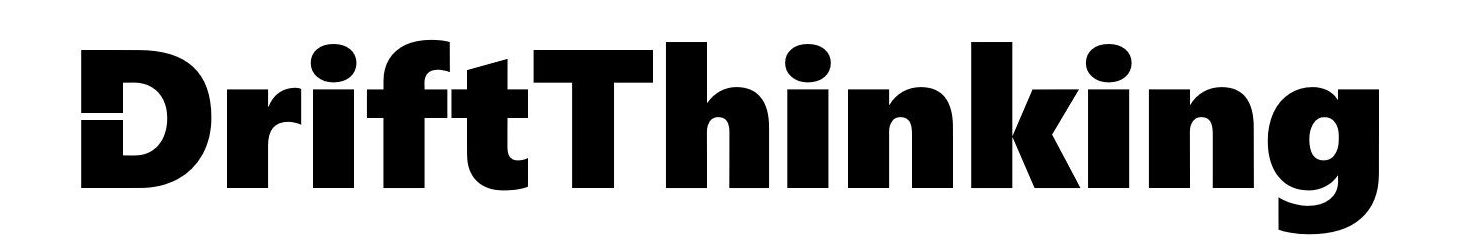私たちは日々、思考を働かせながら生きています。
計画し、判断し、過去を振り返り、未来を描く。
けれど、その思考は本当に自由なものと言えるでしょうか?
多くの思考は、自分で選んだものというより、これまでの経験や環境から“無意識に身についた価値観”や“思考のクセ”によって形づくられています。
「こうあるべき」「もっと頑張らなきゃ」「損をしてはいけない」「他人に認められたい」──
そんな観念が、知らず知らずのうちに、私たちの思考の内側に埋め込まれているのです。
このような価値観やクセの奥には、たいてい“執着”があります。
とりわけ、「自分を守りたい」「得をしたい」「正しく評価されたい」という“利己的な欲求”は、私たちの思考を強く駆動させます。
利己が悪いわけではありません。それもまた自然な人間の働きです。
ただ、気づかぬうちにその欲求に巻き込まれ続けていると、思考のパターンが固定化し、
「なぜ自分ばかりが損をするのか」「なぜ認めてもらえないのか」といった苦しみが生まれやすくなってしまいます。
ドリフトシンキングは、そんな“とらわれた思考”に対して、まずは「眺める」という態度を取ります。
無理に変えようとせず、ただ今ここにある思考・感情・感覚の流れを観察し、そのままの自分としてそこに“居続ける”。
それによって、私たちは自分の中にある「利己的な反応」を否定することなく、その存在を穏やかに受け止めることができるようになります。
そのうえで、ドリフトシンキングが示すもうひとつの可能性があります。
それが「利他」と「因果」という視点の導入です。
●「利他」は、思考のベクトルを変える
思考が利己の方向に傾くと、評価や成果への執着が強まり、それによって苦しみも大きくなります。
けれど、「誰かのために」「世界とのつながりの中で」という視点を持つと、思考の向かう先が変わっていきます。
このとき、思考そのものを捨てるのではなく、思考の主語が“自分だけ”から“他者との関係”へと広がるのです。
その結果、執着の強度が自然と和らぎます。
つまり、利他の視点は、思考のクセとの新しい関係性を築く装置となるのです。
●「因果」は、思考の焦りをほどく
もうひとつの鍵は、「因果」の捉え直しです。
「こうすればこうなるはず」という直線的な期待は、思考に焦りや苛立ちを生みます。
でも、因果の視野を広げれば、“自分が意図した通りに物事が進まないこと”すら含めて、全体の流れの一部として受け取ることができるようになります。
このとき、私たちは“結果を操作しようとする思考”に巻き込まれるのではなく、
「この選択が、どこかで誰かに届くかもしれない」という静かな信頼のもとで、思考と共に居ることができます。
利己を否定せず、思考とともに漂う
「利他」や「因果」は、思考から完全に自由になるための方法ではありません。
むしろそれは、“とらわれがちな思考”と新しい関係性を結ぶための、柔らかな再設計”です。
私たちは、思考を完全に止めることも、執着を一瞬で消すこともできません。
けれど、思考に気づき、利己的な反応を優しく眺め、
その思考の向きを利他へとゆるやかに開き、
因果の中で大きな流れを信じて身を委ねていく──
その営みこそが、ドリフトシンキングが示す「思考と生きる」新しい道なのです。